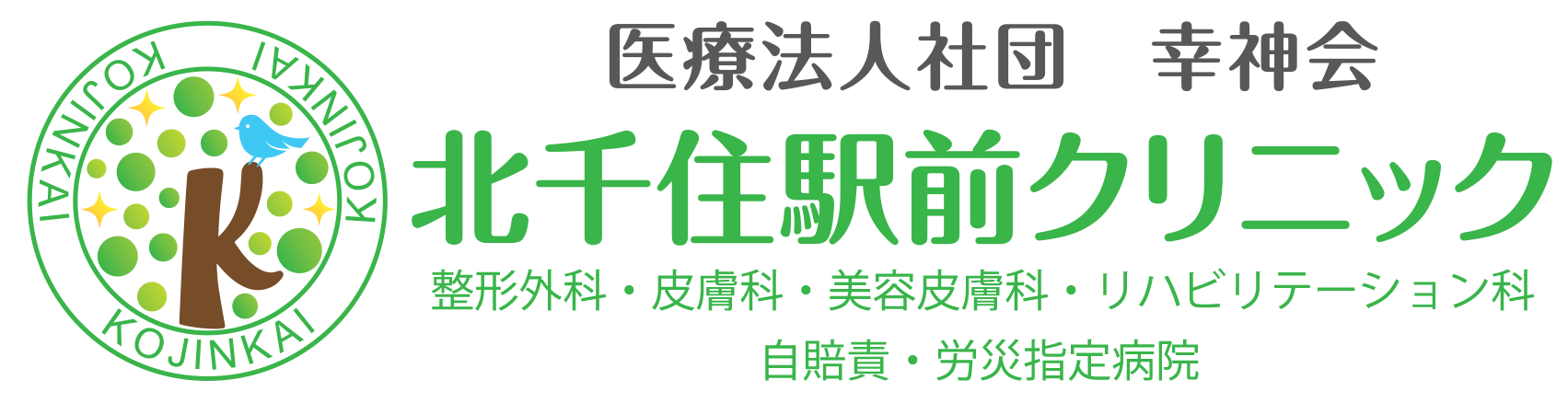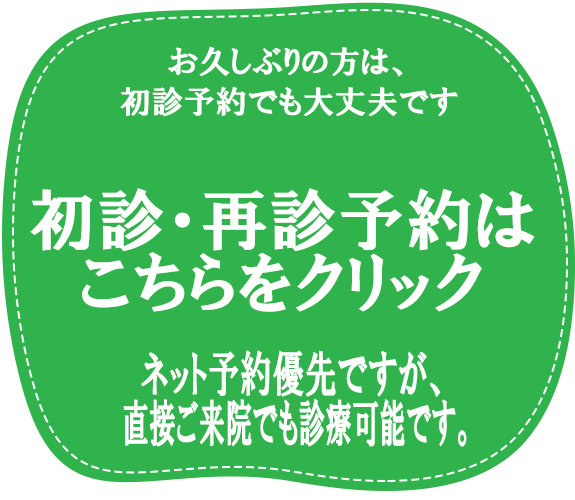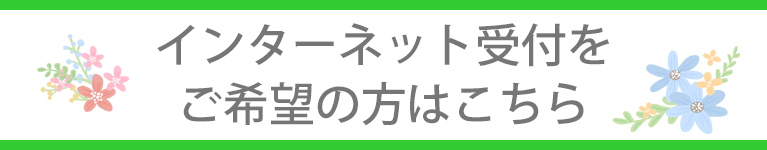皮膚科
アトピー性皮膚炎・乾癬・湿疹・皮膚炎・かぶれ、水虫、水いぼ等のウイルスや細菌性皮膚疾患などの一般皮膚科に加えて、しみ・赤あざ・青あざなどのレーザー治療、およびAGAやEDのお薬処方(自費扱い)を行っております。
毛虱(あたまじらみ)
- 接触により感染します。
- 感染から発症まで約4ヶ月位です。
- 人にだけ寄生し主に頭髪に寄生します。(眉毛、睫毛、体毛にも)
- 幼少児に多く見られます。
- 体長0.18~1.2mmカニに似ていて、肉眼で確認できます。虫体は毛を両側の爪でつかみ皮膚に頭部をつけ、ほとんど動かず、一見かさぶたのようにみえます。
- 卵は長楕円形で毛髪に膠着していて、白色を帯びた微小な卵が頭髪にセメント様物質で固定されています。産卵数は1日に1~4個、卵から成虫になるまで13日~16日かかります。
- 痒みがあり、掻爬のため湿疹化したり二次感染を引き起こします。
治療
- 剃毛すればいいのですが、剃毛が嫌ならシラミ駆除剤(スミスリンパウダー、シャンプー)を使用します。
- 卵は取り、成虫はくしでおとして殺します。
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎の治療薬 コレクチム軟膏を採用いたしました。
詳しくは医師までご相談ください。
アトピー性皮膚炎とは
かゆみを伴う湿疹が見られる皮膚疾患
アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う湿疹が見られる病気です。生後間もなく始まって小児期には自然に治っていくことの多い病気だといわれてきました。しかし、なかなか症状が治らない患者さんや、大人になっても症状が続いているという患者さんが増え、社会問題化して、病気についての情報は一般の方にも広まってきています。
外からの刺激やアレルギーの原因物質が炎症を引き起こす
アトピー性皮膚炎の患者さんの皮膚は、外からの刺激に弱いという特徴があります。皮膚を大切にしなければ、炎症が起こってしまいやすい状態です。また炎症が起こると、さまざまなアレルギーの因子が外から入ってきやすくなります。
皮膚を正常な状態に近づけることでバリア機能を回復させられれば、外からの刺激やアレルギーの原因物質による炎症を防ぐことができます。なるべく早くよい状態をつくりあげ、それを維持することが、アトピー性皮膚炎の対策として重要です。
アトピー性皮膚炎の原因とは?その歴史について
アトピー性皮膚炎の歴史
アトピーという言葉には、遺伝的に見られる奇妙なアレルギーという意味合いがあります。
アトピー性皮膚炎の患者さんのお子さんや兄弟に、同じ症状が見られる頻度が高いことから、遺伝的な素因があるといわれています。また、特定の食べ物やダニなどの影響を受けることが多いことから、アレルギーが原因だといわれてきました。
しかし、特定の食べ物を摂取するのを止めたり、ダニを徹底的に減らす努力をしたりしても、多くの場合それだけでは皮疹の改善が見られません。アレルギーとの関係が完全に否定されるわけではないものの、食事やダニなどが原因というだけでは説明のつかない病気だということです。
さまざまな悪化因子を考慮することが治療において重要
アトピー性皮膚炎はアレルギー疾患の1つとされていますが、皮膚のバリア機能低下、遺伝的素因、アレルギー刺激、ストレスなどが集合して起こる病気です。
アトピー性皮膚炎の患者さんには、炎症を引き起こす物質“サイトカイン"を放出する、ヘルパーT細胞(Th細胞)のタイプ2にあたる“Th2細胞"が活性化しやすいという素因があります。また、皮膚のバリア機能が低下しているため、外からのさまざまな刺激に弱く、引っかいたりこすったりするような刺激だけでも湿疹が出てしまいます。それに加えて症状を悪化させる可能性があるのが、ダニや食物などのアレルギーなのです。
そのため、アトピー性皮膚炎は、さまざまな悪化因子を考慮して総合的な治療を行う必要があります。
アトピー性皮膚炎の診断方法
臨床症状により診断可能
アトピー性皮膚炎は、目で見るだけ、つまり臨床症状で診断できることがほとんどです。湿疹の出やすい部位が年代によって異なるという特徴もあり、それを参考に診断していくため、特に診断の際に検査は必要ありません。例外的な皮疹の患者さんもいらっしゃいますが、検査して初めて分かるような病気ではないということです。
年齢ごとの皮疹の特徴として、次のようなことが挙げられます。
- 乳児期:頭や顔から始まり、しばしば体幹、手足に下降する
- 幼小児期:首や手足の関節に見られる
- 思春期、成人期:上半身(頭、首、胸、背中)に強い傾向がある
たとえば幼小児期のお子さんは、汗をかきやすい肘と膝の内側によく皮疹ができます。診察する際に見ていると、肘と膝の内側を両手で同時にかいて、そこに湿疹ができていることがあります。皮膚がこすれたり汗をかいたりして炎症が起こり、かゆみが出て、引っかいてしまっているのだと分かります。
重症度の参考となる“TARC値”とは
診断や重症度の参考として、血液検査で"TARC値”を測定する場合があります。アトピー性皮膚炎では、Th2細胞が関連して炎症が起こります。Th2細胞が活性化しているときに上昇する血液検査の数値が、TARC値です。
治療を継続するとTARC値が下がってくることから、病気の勢いを調べることにも活用できます。患者さんの治療に対するモチベーションをさらに高めていただけるよう、「こんなにTARC値が高いのだから、病気はまだまだ勢いがありますよ」「TARC値が下がっていますね。だいぶよくなりましたよ」とお話しすることがあります。
大人のアトピー性皮膚炎に関わる、精神的・肉体的ストレスについて
アトピー性皮膚炎とストレスの関係
子どものときアトピー性皮膚炎にかかり、ほとんど治っていたのに成長してから再発した、あるいは成長しても治らないという患者さんの数は、増加傾向にあります。大人になってからのほうが、かえって症状がひどいという方もいます。
大人になってもアトピー性皮膚炎が治りにくいケースでは、精神的あるいは肉体的なストレスの問題が挙げられると考えています。その理由として、ストレスが脳に影響し、皮膚の炎症を引き起こす可能性が分かってきています。
アトピー性皮膚炎の悪化因子となるストレスの種類
たとえば高校生の場合、受験のストレスや、両親が離婚しそうだといった家庭内のトラブルによるストレスなどが、悪化因子になり得ます。
大学生になってもアトピー性皮膚炎が治らないという場合、所属しているサークルで問題を抱えているといった、人間関係におけるストレスが挙げられます。私が経験したなかでは、サークルの代表としてメンバーをまとめなければならなくなり、真面目に取り組もうとするほどストレスがたまって、アトピー性皮膚炎が悪化したという患者さんがいました。
社会に出た後も、上司とうまくいかない、仕事が忙しくて毎日疲れ切っているといった仕事上のストレスなどが、アトピー性皮膚炎の悪化因子になります。
習慣化した掻破行動について
ストレスを上手に解消できないと、かゆいところを引っかく“掻破行動”の異常が起こることがあります。ストレスを回避する、あるいは癒やすために、自分の皮膚をかいてしまい、気持ちがよくて止まらなくなるのです。血が出るほどかいて痛くなるまで、かいたりこすり続けたりすることもあります。
皮膚のバリア機能が低下した状態でかき続けると、炎症はよりひどくなってしまいます。掻破行動により症状が悪化したと考えられる患者さんには、原因が自分自身のストレスだと気付いてもらう必要があります。かくのを止めるのはつらいと思いますが、アトピー性皮膚炎を治したいのなら、引っかくという行為を減らしていくことが大切です。
アトピー性皮膚炎の治療について
アトピー性皮膚炎の治療では、“薬物療法”“外用療法・スキンケア“悪化因子の検索と対策”という3つの観点で、バリア機能の低下した肌をケアすることが重要です。
薬物療法
皮膚の炎症を抑えるためにもっともよい薬は、ステロイド外用剤(塗り薬)です。1990年代、ステロイドへの抵抗や不安を持つ方が増え、ステロイド外用剤を適切に使用せず重症化した患者さんが多く見られましたが、早く炎症を抑えることがバリア機能を回復させ、アトピー性皮膚炎を再燃させないことにつながります。
ステロイド外用剤に代わる案として、タクロリムス水和物という軟こうを使うことがありますが、効果は中程度の強さのステロイド外用剤と同程度です。
皮膚のかゆみに対しては、かゆみを和らげる抗ヒスタミン薬を内服します。
外用療法・スキンケア
炎症がほとんど収まれば、先述したステロイド外用剤などの薬を塗り続ける必要はありません。ただし、炎症が見た目で収まっているように見えても、バリア機能の異常は残っています。無治療でケアをせずにいると、また炎症が起こってしまいます。
バリア機能の状態を維持するために必要なのが、外用療法・スキンケアです。皮膚のバリア機能を改善し、水分を保持するため、保湿剤や保湿クリームを継続して使っていきます。
悪化因子の検索と対策
アトピー性皮膚炎の悪化因子として、衣服や洗浄剤などの皮膚に触れるものに問題がないかを調べ、皮膚に合わない場合は使用しないようにします。
特定の食べ物を摂取することで明らかに症状の悪化が見られる場合は、それを食べないようにします。ただし、一般的にアレルギーの原因になりやすいという理由で、さまざまな食べ物を控える必要はありません。
皮膚のバリア機能が低下した状態では、ダニは症状を悪化させる因子となる可能性がありますが、皮膚のバリア機能が戻ればダニ対策を行う必要は特にありません。
そのほかの悪化因子としてのストレスについては、医師と相談し、悪化の原因がストレスだと気付くだけでも、症状が改善するきっかけになります。
Th2細胞のサイトカインを抑える注射薬“デュピルマブ”の登場
Th2細胞のサイトカインを抑える治療法として、デュピルマブという注射薬が2018年に登場しました。よく効きますが、既存の治療では効果が不十分な重症例のための薬です。保険適用されているものの費用は高額であり、塗り薬が面倒だというような理由では使用しません。
アトピー性皮膚炎の治療はいつまで続けるの?

治療を終了する指標として特に決まったものはありませんが、“気付いたときにはもう、かかなくなっていた”という状態がゴールといえます。塗り薬や飲み薬を使っていない状態で、維持療法としての保湿剤などを忘れても症状が悪化しなければ、治療をすることはなくなっていきます。長年かけて少しずつ、“保湿剤などを塗り忘れても大丈夫だった"という経験を重ねていくことが必要です。
私が診察するときは、患者さんから症状が改善する目安を開かれたら「約1か月後には肌がきれいになって、人に会うのもおっくうではなくなると思いますよ」「約3か月後には、かゆいと言わなくなると思いますよ」といった、患者さんに合った目安をお話しします。
アトピー性皮膚炎との付き合い方のポイント
症状が出てきたらすぐ治療を再開すること
なるべく長い間、保湿剤や保湿クリームによるスキンケアを続けてください。“症状が出てきたようだ”と思ったらすぐに炎症を抑える薬(薬物療法)を使い、炎症が鎮まったらまた保湿剤などによるスキンケアに戻します。そして、症状がひどくならないうちに薬物療法を再開することを繰り返していれば、ほぼ炎症のない状態を保つことができます。
医師と患者さんがよい関係をつくること
患者さんの中には、どうしても症状がよくならない重症例の方もいます。たとえば、ストレスがアトピー性皮膚炎の悪化因子になっていて、そのストレスを解消するのが難しい患者さんです。医師の介入が容易ではない場合もあるためです。
しかし重症例でも、症状をできるだけ抑えることは期待できます。患者さんには、「現在の症状の強さを10として、2か月もあれば2~3まで下げられますよ」というようなことをお話しします。”2~3では治っていない"と思われるかもしれませんが、「現状では、あなたの限度は2~3ですね。でも、もう少し生活を工夫してストレスを減らすと、1にすることができますよ」などと丁寧に話すことで、患者さんはモチベーションを持って治療を続けてくださると思っています。医師と患者さんがしっかりと話し合い、よい関係をつくることも大切です。
アトピー性皮膚炎の患者さんの家族へのアドバイス
いろいろな治療法をすすめず、医師の治療に専念させること
成人の患者さんが受診するときでも、付き添いで親御さんや祖父母の方が同席されることがあります。以前、私は患者さんのおばあさまからこんなことを相談されました。
「アトピー性皮膚炎は私の遺伝です。娘も肌が弱く、孫にも遺伝してしまいました。孫には、アトピー性皮膚炎によいと聞いた方法を何でも試させているのに治らないのです」
それを聞いて私は、「遺伝でアトピー性皮膚炎になったと考える必要はありません。お孫さんの場合、学校のサークル活動で受けているストレスが主な原因です。私が治療しますから、私を信じて治療は任せてください」とお話ししました。
お孫さんにいろいろな治療法をすすめる祖父母の方はよくいらっしゃいますが、適切な治療をしなければアトピー性皮膚炎は治りません。また、たとえば数か月おきに「次はこれをやってごらん」と言われていたら、患者さんも対応するのが大変です。祖父母の方には、なるべくお節介を焼かないということが、アドバイスになる場合があります。
患者さんに対して献身的になりすぎないこと
親御さんの中には、お子さんのアトピー性皮膚炎が心配で、何でもやってあげてしまうという方がいます。しかし、大人になっても食事や洗濯など身の回りのことを何でもやってあげていたら、子どもは親に頼り切ってしまい、お互いに依存する“共依存”の関係になってしまう心配があります。「病院には1人で行ってらっしゃい」と、ある意味で突き放すような姿勢も大切です。
また、アトピー性皮膚炎にはこれがよくない、あれはだめ、などと禁止する必要もありません。何でもさせてあげたほうが、患者さんは、抱えているストレスを上手に発散する方法を見つけやすくなるものです。
股部白癬(インキンタムシ)
青年男子に多く、(稀に女子も)陰股部、臀部に境界明瞭な湿疹用局面が出現します。中央は中心治癒傾向をしめします。(周りが赤く堤防状となり、中は正常にみえます。)
放置すると苔癬化(苔がはえたようになる)から色素沈着にまで及びます。あまり陰嚢まで侵すことはありません。
俗称インキンタムシです。
原因
真菌(カビ)
Tr.rubrum. Epid.floccosum.
治療
抗真菌剤の概要
予後
頑癬と言われるようにしつこい。1日1~2回の外用療法を2~3ヶ月行います。
汗疱(かんぽう)

手掌、足底、指の側面などにみられる水疱性疾患です。多汗を伴うことが多く、夏季に多く、痒みも時にあります。
小水疱は無菌で、原因は不明ですが汗の貯留現象とみなされます。手、足の「あせも」のような疾患です。
また、交感神経と関係しており、緊張すると「手に汗握る」と言いますが、交感神経の分泌物アセチルコリンが出て手足の汗腺が反応し汗が出て悪化します。
昆虫刺症(虫刺され)
昆虫網に属するものには蚊やノミのように吸血、毒蛾、毛虫の針(1匹1万本)またハチのように毒液の注入で人に害を及ぼすものがあります。
蚊科
- アカイエカ、トウゴウヤブカなど2000種類
- 即時型反応は掻痒を伴う紅斑と膨疹1~2時間で消失
- 遅延型反応は5~6時間後に始まり湿潤を伴う掻痒性紅斑で時に水疱を伴い程度は個人差がある。
ブユ科
- 体調2~7mmで雌成虫のみ吸血
- 時期は5月~6月頃
ノミ科
- 体調1~5mmでヒトノミ、ネコノミ、イヌノミ、ネズミノミなどすべて人から吸血する。
ナンキンムシ科
- 体調3~4mmで柱の割れ目、床、壁に潜み夜間吸血に出てくる。
アリ
- 日本だけでも100種類。毒針で刺すオオハリアリ、毒液を撒くアカヤマアリ、下あごでかむオオズカアリなどで刺されると発赤膨張する。
ハチ
- 10万種類。スズメバチ科、ミツバチ科などの被害が多い。ショック死することもある。
ジベルばら色粃糠疹
初発疹が出て7~10日後に急激に体幹、四肢に”しわ”の割線に沿ってまわりに粉をふいたような、または赤い毛包性小丘疹が多発する。手、顔、頭には殆ど発疹は出ない。痒みはあってもわずかです。
20~30代に多く、春・秋に多い。
原因
はっきりと解明されていませんが、次の事が考えられている。
- 病巣感染アレルギー説…風邪を引いた後に出る。
- 自家感作性皮膚炎説…かぶれた後に出る。
- 薬疹の一部…薬を飲んでいる。
治療
ワセリンなどの外用、抗炎症剤、抗ヒスタミン剤など。
予後
通常3~6週間という長い時間かかり、よく病院をわたり歩く人がいるが、待てば消える。皮膚の風邪のようなものです。
主婦湿疹
家事に従事する主婦の手に多く見られます。指背、手背に斑状に発赤、腫脹、丘疹、亀裂などをきたします。
原因は合成洗剤による脱脂、角質水分保持能力低下、機械的刺激、科学的刺激、他物質に対する感受性の上昇など基盤にあると考えられています。
生活
炊事、洗濯時必ず手袋をすること。ゴム手袋でかぶれる人は、中布があるものや、木綿の手袋をつけてからゴム手袋を着用すること。
神経質に手を洗わないこと。
1日数回ハンドクリームで保湿すること。
ひどい部位にはステロイドの入った外用剤を外用すること。
それでも改善しなければテープなどの密封療法をためしてみること。

掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)
手掌、足底に小水疱が出来、直ちに膿疱化してその周りが赤くなり、やがて融合して局面を作ります。掻痒はある人とない人がいます。慢性に経過し時に悪化する難治性疾患です。合併として胸肋鎖骨骨化症があり、鎖骨周囲に痛みを伴うこともあります。(10%)
原因
不明ですが、説として病巣感染アレルギー説、乾癬説、金属アレルギー説(歯科金属)、内分泌障害など種々あります。
治療
原因の除去、例えば歯科金属除去、扁桃腺摘出などを行います。
外用
手掌、足底は皮膚があつくひどい時には強力なステロイド剤は外用し軽快したら弱めます。また密封療法としてテープを使用することもある。内服は状態に応じて免疫抑制剤など。
脂漏性湿疹
皮脂腺が活性化する思春期以降の年齢層に生じ、皮疹が脂漏部位に好発することから皮脂腺の成熟が発症になんらかの関連をもつと考えられています。また、脂漏部位に繁殖するある酵母菌も病因を悪化させると考えられています。
好発部位
- 脂漏部位:頭部、顔面、前胸部
- アポクリン汗発汗部:腋窩、臍窩
生活
顔、体は毎日入浴して石鹸で病変部の皮脂を除去し、頭は刺激のないシャンプー、リンスでよくすすぐようにして下さい。入浴後にひどい時にはステロイドの入った外用剤を外用し、改善したら非ステロイド系消炎外用剤に変えていくようにしてください。
尋常性乾癬
皮膚が赤く盛り上がりその上に乾燥した白い角質が厚く付き、これが大量にはがれ落ちる皮膚疾患です。原因は不明ですが遺伝素因があると言われています。そして免疫機能に影響を与える環境因子が加わると発症すると言われています。
その因子としてストレス、ウイルス感染症、肥満、薬剤などが報告されています。この病気は決して他人にうつしません。
治療
外用療法はステロイド剤またはビタミンD3を使用する。ステロイド剤は長期に使用すると皮膚萎縮など引き起こすことがあるため、軽快したらビタミンD3にかえます。
内服療法は抗アレルギー剤、シクロスポリン、チガソンなど副作用の強いものもあり、必要かどうかよく判断の上内服します。
また光線療法もあります。(PUVA療法)尋常性乾癬
尋常性疣贄
◇液体窒素で治療を受けた方へ
この治療法はマイナス200℃の液体窒素を患部に2~3秒押当てて治療する方法で、人工的に凍傷を起こさせます。
皮膚が赤くなったり、水疱が出来たりします。尋常性疣贅(イボ)は、ウイルス(ヒト乳頭腫ウイルス)が原因ですのでこの方法が効果的です。
経過
2~3日で水疱が出来ます。7~10日で黒くなりカサブタになります。この時無理にカサブタをはがさないでください。
注意事項および処置
感染の原因となるので水疱は無理に破らないでください。足などにもし大きな水疱が出来て歩きにくければ、きれいな針でさし、中の液を出してガーゼまたはバンドエイドを貼っておいてください。
皮膚は浮き上がるようになりますが無理にとらないでください。直接、手指で触れないでください。
蕁麻疹

蕁麻疹は、5人に1人は一生のうちに少なくとも1回は経験するといわれている日常よく起こる病気の一つです。
かゆみを伴い赤く盛り上がる発疹が突然出現し、数時間以内に消失しますが地図状に広がったり、新たに他の部位に出現したりします。時にはまぶたやくちびるがはれたり、まれに呼吸困難が起こることもあります。
このような症状が短期間で治る場合は急性蕁麻疹、1ヶ月以上にわたって続く場合を慢性蕁麻疹と呼んでいます。後者の場合は数ヶ月から数年に及ぶことがあります。
蕁麻疹発生のメカニズム
蕁麻疹は皮膚や粘膜に存在する肥満細胞(マスト細胞)が刺激され、その細胞内に含まれるヒスタミンを主とする化学物質が遊離され、皮膚や粘膜の血管に作用することによって発疹を生じます。
この肥満細胞に対する刺激には、
1)アレルギー性のもの
2)非アレルギー性のもの
の2つがあります。
蕁麻疹の種類と特徴
- 食事性蕁麻疹
食物の摂取によって起こる蕁麻疹です。(仮性アレルゲンを含む)食品に含まれる防腐剤(サリチル酸など)、着色料(タートラジン)が蕁麻疹の原因となることがあります。 - 薬剤性蕁麻疹
薬剤を注射、内服した時に起こる蕁麻疹です。
ほとんどすべての薬剤が原因となりますが、中でも最も多いのがペニシリンなどの抗生剤です。 - 環境因子による蕁麻疹
家のカビ、ほこり、動物のフケ、花粉、タバコの煙などが原因となり生じる蕁麻疹です。 - 人工蕁麻疹
皮膚に圧力を加えてこすることによって生じる蕁麻疹です。皮膚に機械的刺激が加わるベルト、下着のゴムの下などに生じます。 - 温熱蕁麻疹
温風、温熱、温水などによって体温が上昇した時に生じる蕁麻疹です。 - 寒冷蕁麻疹
寒風にあたったり、プールで泳いだり、冷水を飲んだりした時におこる蕁麻疹です。時にくしゃみ、流涙、嘔吐を伴い、まれに頭痛、失神状態に陥ることもあります。 - 水性蕁麻疹
水泳、シャワー、入浴、発汗など種々の温度の水との接触により生じる蕁麻疹です。 - 日光蕁麻疹
日光照射部に一致して生じる蕁麻疹です。一般に皮疹は、日光照射中におこりますが、照射中止後に生じることもあります。 - コリン性蕁麻疹
激しい運動、入浴などの発汗時や精神的興奮が高まった時に生じやすい蕁麻疹です。 - 病巣感染性蕁麻疹
上気道感染、中耳炎、副鼻腔炎、扁桃炎、虫歯、肝炎など種々の感染に伴う蕁麻疹です。 - 心因性蕁麻疹
多忙な仕事、対人関係上のストレス、性格的なものにより過敏な状態となり刺激に対する反応性が高まって蕁麻疹が生じやすくなります。 - 血管浮腫
顔面(まぶた、くちびる)に好発する一過性の限局性浮腫。
普通の蕁麻疹より皮膚の深い所まで生じる変化です。 - 接触蕁麻疹
原因となる物質に触れて生じる蕁麻疹です。植物(イラクサなど)、ハチ、アリ、クラゲなどの接触によるものがあります。
検査
アンケートによりどのような原因で蕁麻疹が起きているかを推測します。それに基づいて疑わしいものについてさらに詳しくチェックします。
- 血液検査
a)一般検査:肝機能検査、病巣感染、その他
b)血清総1gE定量(各種の抗体の総和量に相当)、特異的1gE(ある特定の物質に対する抗体) - スクラッチテスト 皮内テスト
- 皮膚描記
- 寒冷刺激
- 温熱刺激
- その他
食物、薬物などの経口試験、除去テストなど
※当院では血液検査のみ施術中です。
治療
検査により原因がはっきりわかった場合には、その原因を避けるようにします。しかし、慢性蕁麻疹の場合原因がつかめないことが多い為、発疹が続いている間は、抗ヒスタミン剤や抗アレルギー剤で発疹をおさえることになります。これらの薬剤は症状の程度により加減して使います。
薬剤の内服で不十分な場合、非特異的減感作といわれるヒスタミン加ヒト免疫グロブリンを用いた皮下注射を併用していくこともあります。
尚、緑内障、前立腺肥大症の方は、場合によっては抗ヒスタミン剤の内服が出来ないことがありますので、治療前に医師にお知らせください。
生活上の注意
- 肉体的、精神的過労が発疹の誘因となることもあるので、十分な睡眠をとり精神的ストレスは避けるように心がけましょう。
- アルコールや、強い香辛料は、末梢血管を拡張して、かゆみを増強させる働きがあるため、避ける方が良いでしょう。
- 食生活では、防腐剤、保存料、着色料を含んだ加工食品を避けて、新鮮な材料を選び充分に加熱調理してから食べるようにしましょう。
- 入浴は熱すぎる湯、長湯は避けましょう。
- 内服薬を医師の指示に従い正しく服用することが大切です。内服当日あるいは薬剤変更時には、眠気、倦怠感などの副作用の出現に注意してください。(車の運転、高所での作業は避ける)
副作用を生じた場合は医師に相談してください。
表1 蕁麻疹の主たる病型
秀 道広 ほか:日皮会誌 128(12):2503-2624(2018)c日本皮膚科学会より引用
I. 突発性の蕁麻疹 spontaneous urticaria
- 急性蕁麻疹 acute spontaneous urticaria(発症後6週間以内)
- 慢性蕁麻疹 chronic spontaneous urticaria(発症後6週間以上)
II. 刺激誘発型の募麻疹(特定刺激ないし負荷により皮疹を誘発することができる蕁麻疹)inducible urticaria*
- アレルギー性の蕁麻疹 allergic urticaria
- 食物依存性運動誘発アナフィラキシー FDEIA
- 非アレルギー性の蕁麻疹 non-allergic urticaria
- アスピリン蕁麻疹(不耐症による募麻疹)aspirin-induced urticaria(urticaria due to intolerance)
- 物理性蕁麻疹 physical urticaria(機械性蕁麻疹 mechanical urticaria,寒冷蕁麻疹 cold urticaria, 日光蕁麻疹 solar urticaria, 温熱蕁麻疹 heat urticaria, 遅延性圧蕁麻疹 delayed pressure urticaria, 水蕁麻疹 aquagenic urticaria)
- コリン性蕁麻疹 cholinergic urticaria
- 接触蕁麻疹 contact urticaria
III. 血管性浮腫 angioedema
- 特発性の血管性浮腫 idiopathic angioedema
- 刺激誘発型の血管性浮腫 inducible angioedema(振動血管性浮腫 vibratory angioedemaを含む)
- ブラジキニン起因性の血管性浮腫 bradykinin mediated angioedema 7
- 遺伝性血管性浮腫 hereditary angioedema(HAE)
IV. 蕁麻疹関連疾患 urticaria associated diseases
- 蕁麻疹様血管炎 urticarial vasculitis
- 色素性蕁麻疹 urticaria pigmentosa
- Schnitzler症候群およびクリオピリン関連周期熱症候群
※国際ガイドラインでは、6週間以上続く蕁麻疹は刺激誘発型の募麻疹を含めて chronic urticariaに分類される。
接触性皮膚炎
接触源が皮膚に付着し、付着した部位に一致して発症します。一時性とアレルギー性とがあり、治療は接触源を絶ちステロイド外用剤を外用します。場合により内服も行います。
接触源となるものには、化粧品、草木、染髪料、帽子、眼鏡、石鹸、洗剤、農薬、セメント、ゴム、革製品、指輪、医薬品、絆創膏、衣類、化学薬品、薬湯、合成樹脂、染料、塗料、装身具、このように多岐にわたります。
帯状疱疹
水ぼうそうのウイルスと同じです。何年も前のウイルスが潜伏していて、生体の感染防御能が落ちると再び活動します。また、他人に水痘を伝染します。
- 片側のみに痛み
- 赤くなりそのうち水疱、びらん
- 3週間で皮膚は治るが痛みが残る人がいます。(帯状疱疹後神経痛)
内服薬
※妊娠中は内服できません。
※すべて1日3回毎食後に内服
- 抗ウイルス薬(白)
バルトレッスを2錠ずつ1日3回医薬と一緒に内服 - 痛み止め(黄)
ボルタレンを2錠ずつ3回内服。痛くなければ痛い時のみの頓服でもよい。 - メチコバール(赤)
1回1錠ビタミンB12で神経再生の時必要となります。 - ムコスタ(ピンク)
1回1錠。医薬外用剤。
注意事項および処置
入浴後に外用してガーゼをしてください。無理はせず、じくじくしていなければ入浴してください。
吐気、頭痛、高熱がある時は入院になります。
伝染性軟属腫
ミズイボ(water wart)とも呼ばれ、一般に小児にみられ、接触により感染します。アトピー性皮膚炎患児に多くみられ、プールでの感染が問題となっています。
原因はウイルス感染でポックスウイルス科伝染性軟属腫ウイルスの感染が原因です。毛包から感染し、細胞質内で増殖して細胞質内にmolluscum(モルスクム)小体と呼ばれる封入体を形成します。
粟粒大ないし大豆大までのドーム状腫瘍で表面平滑で蝋様の光沢があり、ピンセットでつまむと乳白色の粥状物質が圧出されます。数個あるいは無数に、散在性ないしは集族性にみられます。
治療
ピンセットで一つ一つ摘み取るのが最も確実な方法です。その他液体窒素療法、硝酸銀塗布などがあります。どうしても取りたくない人は自然消退を待ちます。増やさないようにアトピー性皮膚炎の治療も並行して行うようにしましょう。
伝染性膿痂疹(とびひ)

【とびひ】は細菌感染症です。黄色ブドウ球菌によるものが主ですが、最近は連鎖球菌によるものも増えてきております。前者は夏に見られ水疱を伴うことが多いことから【水疱型】とよばれ、まれに全身につき火傷のようになることがございます。後者は1年中見られ痂皮(かさぶた)を伴うことが多い為【痂皮型】とも呼ばれます。割合としては、おおよそ前者が90%、後者が10%程度となります。時に腎炎を合併することがございます。
経過
乳幼児の顔面、体、手、足に水疱がつぎつぎに発生し、容易に破れてびらん面となり黄色の痂皮がつきます。
虫刺、かぶれ、アトピー性皮膚炎など小さな傷のある子供に伝染しやすい傾向がございます。
注意事項および処置
細菌は爪の下、鼻の中、耳の中にひそんでいます。爪を切ることと外から帰ってきたら石鹸で手を洗うようにしてください。広範囲の時は幼稚園、保育園は他児への感染の恐れがあるため休ませてください。
薬は抗生物質の内服と外用を行います。入浴前後に外用するようにしてください。
皮脂欠乏症湿疹
角質層の水分保持能力が低下すると皮膚は乾燥します。高齢の方に多く、また空気から乾燥する秋から冬にかけて多くみられます。
入浴の際、石鹸で垢すりをしない、イオウの入った入浴剤を入れない。入浴後保湿剤などによるスキンケアを心がけることが大切です。
粉瘤(おでき)
通常、皮膚面よりわずかに、あるいは半球状に隆起する鶏卵大までの表面平滑、ほぼ皮膚色で下床とは可動性、弾性硬の皮膚腫瘤で、時に二次感染を来たし、発赤して圧通があります。(炎症性粉瘤)
治療は全摘出手術が好ましいが、二次感染を呈している場合は、小切開を加えて圧迫して悪臭のある粥状内容物を排泄し、消毒し、内容物をガーゼなどのドレーンを使用して排泄させます。この間抗生剤の内服や点滴で二次感染を抑えます。ガーゼを挿入している場合は、連日の通院が必要です。
注意事項および処置
もしぬれたり取れたりしたら中の内容物を押し出し、抗生剤の外用剤をつけてバンドエイドまたはガーゼでふさいで下さい。
ヘルペス
ヘルペスウイルスは初感染した後に知覚神経を伝わって上行し、神経節に潜伏します。そして過労、ストレス、紫外線照射、風邪をひいたときなどさまざまな誘因で活性化し神経を下行して、その支配領域の皮膚粘膜で増殖し、口唇ヘルペス、角膜ヘルペス、陰部ヘルペスとして再発します。
再発型は初発時ほどウイルスの増殖は活発ではなく病変部も限られます。このような時は抗ウイルス剤の外用剤で対処することが可能です。しかし場合により抗ウイルス剤の内服も必要な時もあります。
・抗ウイルス剤の外用剤
アラセナ軟膏、ゾビラックス軟膏など1日2~3回患部に外用する。
・抗ウイルス剤の内服
バラシクロビル500mgの場合は朝、夕食後に1錠ずつ内服。
ゾビラックス200mgの場合は5錠を1錠ずつ5回にわけて内服。
ファンビル250mgの場合は3錠を朝、昼、夕食後に1錠ずつ内服します(妊娠の可能性がある人は内服できません。)
乳児脂漏性湿疹
新生児期から乳児期初期には、生理的に脂腺機能が亢進し、脂漏性鱗屑(かわいたような、ふけのような)を付着した紅斑が、頭部、顔面、前頸部、腋窩、おむつ部位に現れ、あまり痒くありません。アトピー性皮膚炎に移行する例もあり鑑別がむずかしいこともあります。
生活
顔、体は毎日入浴して石鹸で病変部の皮脂を除去し、頭は毎日洗髪してよいが、刺激のないシャンプー、リンスでよく「すすぐ」ようにします。入浴後、ひどい時にはステロイドの入った外用剤を外用し、改善したら非ステロイド系消炎外用剤にかえていくようにしてください。
水虫
真菌(カビ)のなかの白癬菌が角質層に感染してケラチンを食べて生きています。角質のあつい手、足はなかなか薬が浸透しにくく治りにくいのです。特に爪に侵入した時は内服薬を使用します。爪は生え揃うまで6ヶ月~1年かかるためその間内服を続けなくてはなりません。
肝臓、腎臓の機能障害がある方は内服できません。また2ヶ月ごとの血液検査が必要です。内服できない方は爪に効く外用剤も開発されました。
水虫の薬はたまに「かぶれ」を引き起こすことがあります。外用して悪化したり赤くなった時には直ちに外用を中止して来院してください。